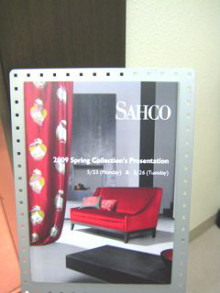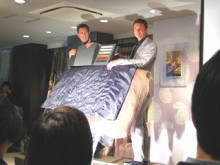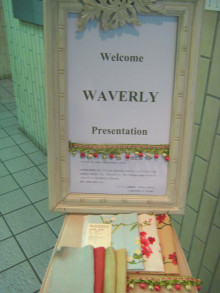ミラノ中央駅からバスに乗って、来たときとは違う小規模な「リナーテ空港」へ向かいました。
空港には日本人らしき人は1人も見当たりませんでした。
外国に来たって感じで嬉しくなってしまうのは、私だけではないはず・・・。
バルセロナに向う機内では、イタリア人の若者男子チームのワイワイ旅行にはさまれてうるさくてしょうがない!!
しかも私の前はたいそうなおデブちゃんで、離陸する前からリクライニングされてとっても苦しいフライトでした・・・ (´0ノ`*)
しかし我慢も2時間程で無事バルセロナに到着しました。

【上空から見たサグラダ・ファミリア】
空港から重たいスーツケースを引きずり々シャトルバスに乗って市内中央の「カタルーニャ広場」へ向かいました。
広場の一角の地下にある観光案内所によって予約していたBus turistic(バス・ツーリスティック)のチケットを受け取りに行きました。
これは、観光客向けに、市内各地の名所を結ぶルートを巡回しているバスで、 バルセロナ市観光局が主体となって、長年運行しているバスなので、使いやすさや利便性は折り紙つきとの事なのです。
事前にインターネットで調べて予約していたのでした。
私達の滞在するホテルは市街中心部から少し離れているので、メトロに向い、また回数券を買うことにしました。
そこでまたまた変なヤツに遭遇・・・ 白人の」男性が財布を落としたので、メトロの代金を貸してほしいと近寄ってきたのです。
これは、観光地特有の詐欺だと解っていたので、無視して過ぎ去りました。
案の定翌日またそこを通ると同じ人が観光客らしき人に同じことを言って擦り寄っていました。
外国で怪しいやつには要注意です! 日本でも同じですよね (;^_^A)v
ウチの奥さんはミラノでもミサンガ詐欺に合っていたので、ガードも厳重になっています。
(手首に勝手にミサンガ結ばれてお金をせびられてました!)
そんなこんな やっとのことでホテルまでたどり着きました。
そこでまた一悶着・・・
ミラノで滞在したホテルでこの日から泊まるホテルのバウチャーも一緒に渡してしまっていたのです。
私は、どうすんの!!って奥さんに八つ当たりしていたのですが、すんなりチェックインすることが出来ました。
(心せまくてすいません・・・ だってもしも泊まれなかったらどうしよーって思うでしょ・・・。(^o^;)
ホテル「アムレイ・ディアゴナル」は近代的で清潔感があってとってもGOODでした。
2人とも移動でくたくたでしたが、スペインに着いたらバル廻りだー!!! と決めていたので、夜の街に繰り出しました。
歩いてみるとホテルの横から続く道は公園通りになっていて、バルやレストランが沢山ありました。
通りにテーブルを出して皆食事やお酒を楽しんでいます。
そのうちの一件の入りました。

まずは、いわしのオリーブ酢漬け、オリーブの実をつまみにビールで乾杯!!!
その後は、「お勧めは?」
「えびが旨いよ!」
「じゃあ それー!」
「隣の人が食べてる ムール貝旨そー!」
「ワインたのもーか?」

「ビーノ・ブランコ プリーズ !」
「あれ ビールのお代わりが出てきちゃった!」
「ま いっかー 飲も 飲も・・・」
「でも ワインも飲むからね~!!」
そうして、バルセロナの初日の夜は更けていきました・・・。